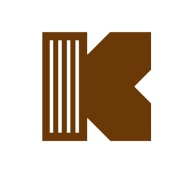「予算オーバーしました…」は、よくある話
「土地と建物の合計で3,000万円に収めたいんです」
最終的な契約額が3,400万円、3,600万円…と上がってしまうケースは珍しくありません。
その原因の多くは、“建物本体”ではなく、“付帯工事・外構・オプション”に潜んでいるのです。
この記事では、「建物価格を抑える現実的な方法」を紹介していきます。
建物価格の内訳を知ることがスタートライン
「建物価格」と一口に言っても、実は以下のように分類されます。
| 項目 | 内容例 |
|---|---|
| 本体価格 | 壁・屋根・キッチン・お風呂など基本構造 |
| 付帯工事費用 | 給排水・ガス・電気などの引き込み |
| 外構費用 | 駐車場・庭・塀・門柱など |
| オプション費用 | 食洗機・浴室乾燥機・照明・コンセント増設 |
| 諸費用(登記など) | 登記・火災保険・つなぎ融資手数料など |
**多くの方が見逃しがちなのが、「オプションと外構の膨張」**です。
だからこそ、最初に「どこまでを見積もりに含むか」をハウスメーカーや工務店と丁寧に確認することが重要です。
建物価格を抑える実践テクニック20選
以下は、効果的かつ大きく利便性を損なわない「コストダウン例」です。
◎構造・間取りの工夫
-
総2階にする(基礎・屋根の面積を最小化)
-
正方形に近い形状にする(複雑な形はコスト高)
-
建物面積を30坪以内に抑える
-
トイレを1つにする(2階トイレを削減)
◎設備・仕様の見直し
-
システムキッチンのグレードを下げる(例:ラクシーナ→V-style)
-
浴室のTV・ミスト機能は後付けにする
-
洗面台は市販品(IKEA・ニトリ)に切り替え
-
造作家具は最小限にし、収納は可動棚ベースに
◎外構・照明・内装の工夫
-
外構工事は引き渡し後に別業者で施工
-
ウッドデッキはDIYや後付けで対応
-
照明は施主支給(ネット購入+電気屋取付)
-
クロスは標準仕様から大きく逸脱しない
◎見落としがちなポイント
-
換気システムのグレードを要検討(第1種→第3種)
-
エアコンは引き渡し後に家電量販店で設置
-
玄関ポーチ・門柱・ポストを後回しに
-
防犯カメラ・センサーライトも後設置可能
◎FP的コスト管理視点
-
頭金を増やして借入額を抑える
-
団信の金利上乗せを下げる工夫(保険選択)
-
火災保険をネット型にして節約
-
固定費(通信費・電気ガス)見直しとセットで家計全体を最適化
削ってはいけない「3つのコスト」とは?
節約ばかりを意識すると、**“将来にツケが回る後悔ポイント”**を招きます。特に、以下の3点は削減非推奨です。
1. 耐震性
→ 壁量計算や耐震等級2以上は家族の命を守る「生命保険」レベルの重要性。
2. 断熱性能
→ 高断熱=光熱費の削減。数十年単位での「住宅の燃費」に直結します。
3. コンセント・配線計画
→ 新築後に「ここにも欲しかった!」と後悔する筆頭。追加工事は高額。
「安く」ではなく「賢く」かけるお金へ
FPとしてよく伝えているのは、初期コストとランニングコストのバランスです。
-
高性能の断熱材は初期費用は高くても、月々の光熱費を抑えてくれる
-
逆に、オーバースペックなキッチンや照明は“見た目満足”でしかない
つまり、「将来どこでお金が出ていくか」を見据えたコスパ設計が本当に大切なのです。
【まとめ】建築費用は「引き算」よりも「賢い選択」でコントロールする
予算内に収めることは、単なる節約ではなく「希望を整理するプロセス」です。
-
自分たちにとって本当に必要な空間・機能は何か?
-
その費用対効果は長い目で見てどうか?
そう考えていくと、満足度はそのままに、価格だけを抑える家づくりが見えてきます。
これから家を建てるすべての人に、「後悔のない賢い選択」をしてもらえたら嬉しいです。
ブログ監修:日比幸平
保有資格:宅地建物取引士・ファイナンシャルプランニング技能士2級 他